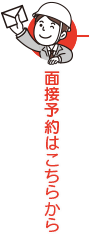「土木工事業界って今どのような状況なの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。近年の土木工事業界は、東京オリンピックが終わったことで工事ラッシュが減少して、新型コロナの影響から工事の数の減少・中断もありました。そのように、土木工事業界は一時不調と言える状況になりましたが、最近では自然災害による復旧工事の増加やインフラ整備の受注増加などがあり、堅調な推移を示しています。以下で、土木工事業界の動向についてさらに詳しく解説します。
土木工事業界の需要は安定している
東京オリンピック終了によってオリンピック需要は減ったものの、オリンピック開催によって延期していた案件があったり、大阪万博や国土強靭計画などの大規模なプロジェクトがあったりと、この先も建設バブルが続いていくことが予想されます。また、地震や台風などが起こったため、災害復旧工事も必要となります。このようなことから、今後も土木工事業界の需要は安定していると言えるでしょう。
インフラ設備の老朽化に対応する必要がある
大部分のインフラ設備は、高度成長期より後に建てられたものです。国土交通省では、社会資本の老朽化について、今後20年の間に建設されてから50年以上になる施設の割合が高くなると発表しました。さらに、2033年になると道路橋や水門などの河川管理施設では、建設してから50年経つ設備が約60%以上もの割合を占めるだろうと予測しました。つまり、全国的にインフラ整備の対応が必要となっているため、土木工事業界の需要も増加していると言えます。
ICTやAIを取り入れたシステム開発が進んでいる
土木工事は働く方にとって負担のかかる作業が多く、その上人手不足という課題も存在しているため、早急な対応が求められています。そのような課題を解消するために、ICTやAIを現場にも取り入れることにより、業務の効率化を目指す動きが進んでいます。例えば、AIによって施工パターンを選ぶ、ドローンを活用して3次元測量をするなどが挙げられます。このようにICTやAIを使って、今後も土木工事業界での業務効率化が行われるでしょう。
土木工事業界は需要が安定していて、堅調な業界です
上記で述べたような、大阪万博などの大規模プロジェクトや、自然災害による復旧工事、老朽化が懸念されるインフラ設備の整備などに今後は予算が投入されます。また、国内での安定した需要だけではなく、最近ではアジアや北米など海外でインフラ展開していく動きもあるので、土木工事業界はこの先も堅調な業界と言えるでしょう。